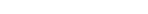おせち料理の盛り付け方(重箱)

重箱でのおせち料理の詰め方
保存しやすく、そのまま振る舞いやすい重箱。
一般的なおせちは、重箱の段数によって詰める料理が決まっています。
※おせちの種類の詳細は、「おせちに入れる料理の種類」をご覧ください。
| 二段重 | おせち料理の種類 |
|---|---|
| 一の重 | 祝い肴・口取り |
| 二の重 | 煮物 |
| 三段重 | おせち料理の種類 | |
|---|---|---|
| 一の重 | 祝い肴・口取り | |
| 二の重 | 焼き物・酢の物 | |
| 三の重 | 煮物 | |
| 四段重 ・ 五段重 |
おせち料理の種類 |
|---|---|
| 一の重 | 祝い肴 |
| 二の重 | 口取り・酢の物 |
| 三の重 | 焼き物 |
| 四の重 | 煮物 |
| 五の重 | カラの重 ※五段重の場合、五段目は「神様からの福を詰める場所」としてカラにするという習わしがあります。 |
重箱での盛付け方の種類
お重の盛り付け方には、伝統的なものでも様々な種類があります。
その中でも代表的なものをご紹介いたします。
-
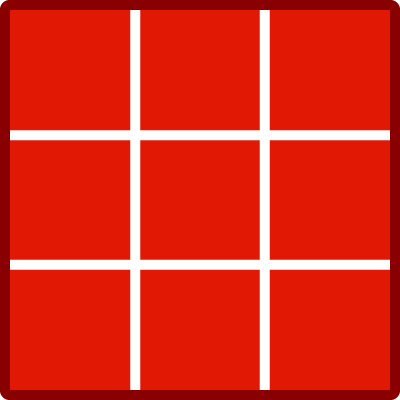
-
田の字・市松
「田」の漢字や碁盤のように、お重を正方形に仕切る詰め方です。
一般的にはお重を4分割した詰め方を「田の字」、それ以上(主に9分割)に分割した詰め方を「市松」と呼びます。
-

-
段詰め(段取り)
お重を横長の長方形に仕切る詰め方です。スペースが広いので、量の多い料理にも対応しやすいとされています。
基本的には3段に仕切りますが、料理に合わせて仕切りを増やしたり、一部縦方向に仕切ったりすることもできます。
-

-
升掛け(手綱)
段詰めを45度傾けたような、お重を直線で対角線上に仕切る詰め方です。
一般的には3つまたは5つに仕切りますが、仕切りの数や位置を変えて様々な詰め方が楽しめます。
-

-
扇詰め
升掛けを曲線状に仕切ることで扇が重なったように見える詰め方のことは扇詰めと呼ばれています。
美しく華やかな印象に仕上げたいときにおすすめの詰め方です。
-
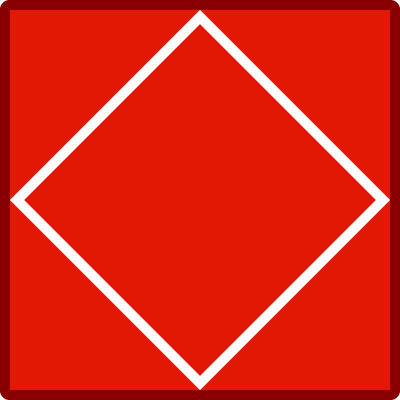
-
七宝詰め(隅切り)
お重の中央に大きなひし形を配置した詰め方です。日本の伝統的な模様である「七宝紋」のように見えることから七宝詰めと呼ばれています。
中央のひし形部分の中を正方形で仕切ることで、さらに豪華な見た目になります。
-

-
末広
丸い小鉢などをお重の中央に配置して、そこから四隅に向かって仕切りを設置する詰め方です。
小鉢には数の子やえびなど、おせちの主役になるような見た目にも華やかで贅沢な料理を入れると、おめでたい雰囲気を高められます。
-

-
八方詰め
重箱の手前側が八の字になるように仕切る詰め方のことは「八方詰め」と呼ばれています。
八の字が富士山のように見えるため、縁起の良い盛り方ともいわれています。